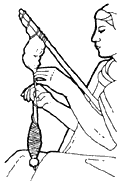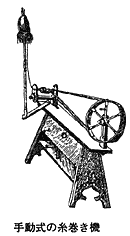【眠り姫】の広がり/様々な解釈/眠り姫は犯されたのか?/茨の垣、炎の壁/死と眠りと忘却/
死に針と眠りの棘/奪われた腕輪/墓の中の馬/女への恐怖/初夜権と純潔の刀
グリムやペローの眠り姫は、紡錘を触るうちに針に刺されて死の眠りについた。
しかし、これは奇妙である。紡錘には針など付いていないからだ。「眠れる美女と子供たち」では紡錘の尖った先が刺さったとしてあるが、実際には刺さるほど尖ったものではないだろう。より古い文献の眠り姫たちが亜麻の繊維を指先に刺している点を考慮するに、細かい部分が亡失されて「紡錘を手に取ったら何かがチクリと刺さった」とだけ語られてしまい、それが「紡錘の先が刺さった」、「紡錘を手に取ったら針が刺さった」と表現されるに至ったものだろうか。
|
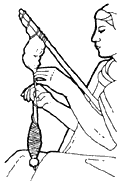
↑手作業での糸紡ぎ。脇に挟んで突き出されているのが糸巻き棒(竿)で、先に亜麻や羊毛などの繊維を縛り付けてある。これを引き出し、湿した指先で縒って糸にして、下にぶら下がっている紡錘(つむ)に巻き取っていく。紡錘の下には石の重りが付いていて、重みで調子よく回せる。糸巻き棒や紡錘の形は様々ある。
|
|
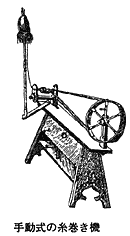
↑やがて糸紡ぎも機械化された。この他にも足踏み式などがある。
左端に突き立っているのは糸巻き棒。この機械では、紡錘はその下に横に寝ている。
|
けれども、それだけで片付けてはしまえない部分もある。視野を広げて類縁話群である【白雪姫】を見ていくと、糸紡ぎに関係なく、針で指を刺されて死の眠りにつくモチーフが存在しているからだ。
たとえばスコットランドの「金樹と銀樹」では、娘を迫害する母親が「せめて指だけでも見せてちょうだい」と頼むので鍵穴から小指だけ出したところ、毒針を刺されて死の眠りにつく。アルバニアの「金の履物」では継母が同じようにする。
しかし針を指に刺す事例はそう多くはない。最も多く見られるのは、針を頭に刺すパターンだ。これは【三つの愛のオレンジ】にも見られる。(こちらでは死の眠りにつくのではなく、鳥獣の姿〜霊魂に変わって飛び去るのだが。)多くの場合、悪い女が「髪を奇麗にしてあげよう」と偽って針を差し込む。針と言うと縫い針のようなものをイメージしてしまいがちだが、この場合は装飾品の意味合いらしく、簪とでも考えた方が分かりやすい。白雪姫が頭に差し込まれる櫛も、このバリエーションとみなすことができるだろう。
世界中の説話に共通した、生死を操る呪具は幾つかある。有名なのが《死の水、生命の水》や《死の果実、生命の果実》。ややマイナーなものに《死に鞭、生き鞭》、抜いただけ(または触れただけ)で敵を殺す一撃必殺の剣、そして《死に針、生き針》などがある。果実と鞭は、どちらも生命樹信仰に由来する。果実は言わずもがなだが、鞭とは木の枝のことだ。魔法の杖と同じで、生命の木の生命力を触れることで対象に移す、という観念による。では、針は何に由来するのだろう。
残念ながら、私にはよく分からない。ただ、『日本書紀』巻二十四にある、鞍作得志の「死神の名付け親」を思わせるエピソードを見ていると、どことなく鍼灸治療の鍼を思い出しもするのだが、どうなのか。
『日本書紀』巻二十四 皇極天皇四年四月戊戌朔
高麗の学僧らは言った。
『同学の鞍作得志は、虎をもって友となし、その術を学び取った。あるときは枯山を変えて青山となし、あるときは黄土を変えて白水とした。種々の奇しき術を究め尽くさないことはなかった。また、虎が針を授けて言うことには、決して人に知られてはならない。これを使えば病が癒えないということはない、と。果たして言ったとおり、癒えないということがなかった。得志は常に、その針を柱の中に隠し置いていた。後に、虎はその柱を割って、針を取って走り去った。
高麗の国は、得志が帰国したがっていることを知って、毒を与えて殺した』と。
日本の民話にも《死に針、生き針》の登場する【夢見小僧】という話群がある。本州から九州まで分布している。
灰坊、または抜け作だと周囲に馬鹿にされている男、もしくは学問所の少年が、ある年の正月に素晴らしい初夢を見たらしいのだが、ニヤニヤするばかりで誰にも内容を教えない。目上の者(主人/親/師匠)は怒って彼をウツボ船に入れて流す。
男は異界(鬼ヶ島)に流れ着き、冥界神(鬼/河童/天狗)と出会う。冥界神は男が恐れずにニヤニヤしているのを見て夢の内容を聞きたがり、「空を飛んで素早く移動できるアイテム(千里車/千里棒)」「刺すとたちまち死ぬ死に針」「刺すとたちまち生き返る生き針(撫でるとたちまち生き返る生き棒)」等の三つの呪具と引き換えに聞き出そうとする。しかし男は死に針を手に入れるなり、冥界神を刺して殺す。または飛ぶ呪具に乗って逃げ去る。
長者の家で娘が死んで嘆いている。男は娘を生き針で刺して生き返らせ、婿に迎えられた。類話によっては、もう一軒別の長者の家でも娘を生き返らせ、どちらの家からも婿になってくれと切望されたので、年(または月)の半分ずつ、両方の家で暮らすことにになったという豪華な結末。
夢の内容を誰にも明かさなかったので、初夢が正夢になった、という話。
※この死に針は、類話(秋田県 東成瀬村)によっては同じ針の一方で刺すと死に、反対側で刺すと生き返ることになっており、アイルランドのダクダ神が持つという、一方で殴るとたちまち死に、もう一方で殴ると生き返る棍棒とよく似ている。
ただ、これらの話群に出てくる死に針は、チクリと刺しただけで死ぬもので、刺さっている間だけ死んでいて抜けると目を覚ます、【眠り姫】や【白雪姫】を眠らせた、そして以下に紹介する、若者を一時的に眠らせたような針とは異なっている。
処女王 ロシア(AФ232)
昔、ある商人がいた。妻と死に別れたので一人息子のイワンに守り役をつけ、しばらくしてから後妻をもらった。ところがイワンはもう成人していて大変な美青年だったので、継母は彼を好きになってしまった。
ある日、イワンと守り役が小さな筏で海に漁に出ると、三十隻の船団が近づいてくるのが見えた。船団は筏の傍に錨を下ろし、三十人の義妹を従えた処女王が現れて、かねてよりお慕いしておりました、あなたに逢うためにここまで来たのです、とイワンに打ち明けた。二人はすぐに婚約を交わした。やがて処女王は、明日も同じ時刻にここへ来るように言い残すと、別れを告げて舳先を返した。
イワンは家に帰って夕飯を食べてから眠った。継母は守り役を呼ぶと酒を勧めて酔わせ、今日は何か変わったことがなかったかと尋ねた。守り役は全てを話して聞かせた。それを聞くと、継母は守り役に留針を渡して言った。
「明日その船が近づいてきたら、イワンの服にこの留針を刺しなさい」
守り役は承知し、あくる日、遠くに例の船が見えるとすぐにイワンの服に留針を刺した。するとイワンは言った。
「おや、なんて眠いんだろう。少し横になって眠るとしよう。ねえ、お願いだ。あの船が近づいて来たら起こしておくれ」
「ええ、必ず起こしてあげますよ」
やがて処女王の船が錨を下ろし、使者がやって来てイワン王子を呼んだが、揺すってもつついても彼は決して目を覚まさなかった。処女王は「明日もイワンをここへ連れてくるように」と言い残すと錨を上げ帆を張って行ってしまった。処女王の船が去ると、守り役は留針を引き抜いた。イワンはたちまち目を覚まして跳ね起き、処女王に引き返すよう呼びかけたが、船はもう遠くに去っていて届かなかった。イワンは悲嘆に暮れて家に帰った。
継母はその晩も守り役を呼んで酔わせ、同じように話を聞き出して、留針を刺す指示をした。おかげであくる日も同じことになった。処女王は、明日もう一度来るようにと言い残した。だがその晩も継母は守り役を呼び、針を刺す指示をしたのだ。
三日目、針を刺されて眠るイワンを処女王の使いはどうしても起こせなかった。処女王は、これが継母の策略であり、守り役が裏切っていることに気づいた。そこでイワン王子に手紙を残し、帆を上げて広い海に去って行った。
針を抜かれて目を覚ましたイワンは大声で処女王を呼んだが、もはや無駄だった。守り役が処女王の手紙を渡してきたので読むと、守り役が裏切っているので首を刎ねるように、そしてもしあなたが私を愛しているなら、山越え谷越えこの世の果てまで私を探しに来てほしいと書いてあった。読み終わるとすぐに、イワンは刀を抜いて守り役の首を刎ねた。そして家に帰って父親に別れを告げ、この世の果てを目指して旅立った。
長かったのか短かったのか。どれほど歩いたのかは知らないが、イワンは一軒の小屋に着いた。それは広々とした野原の中央にあり、鶏の足の上に建ってぐるぐる回っていた。中に入ると、骨の一本足のババ・ヤガー(山姥)がいた。
「くん、くん。ロシア人の匂いがする。今までロシア人の臭いをかいだこともなければ姿を見たこともなかったが、今日は向こうからおでましかい。自分で望んで来たのかね、嫌々ながら来たのかね」
「仕方なくさ。この世の果てがどこにあるか知っているかい」
「知らないね。だが私の妹なら知っているかもしれないから、そこへ行くがいい」
イワンは礼を言って旅を続けた。少しも休まずに先を急ぎ、どれほど歩いたのか知らないが、前と同じような場所にある同じような小屋に着いた。この中にもババ・ヤガーがいた。
「くん、くん。ロシア人の匂いがする。今までロシア人の臭いをかいだこともなければ姿を見たこともなかったが、今日は向こうからおでましかい。自分で望んで来たのかね、嫌々ながら来たのかね」
「仕方なくさ。この世の果てがどこにあるか知っているかい」
「知らないね。だが私の妹なら知っているかもしれないから、そこへ行くがいい。
もし妹が怒ってお前を食べようとしたなら、ラッパを三本吹かせてくれと頼むんだよ。一本目は低い音で、二本目は少し高く、三番目はうんと高い音で吹くがよい」
イワンは礼を言って更に旅を続けた。どれほど歩いたのか知らないが、とうとう、前と同じような場所にある同じような小屋に着いた。この中にもババ・ヤガーがいた。
「くん、くん。ロシア人の匂いがする。今までロシア人の臭いをかいだこともなければ姿を見たこともなかったが、今日は向こうからおでましかい」
ババ・ヤガーはそう言って、押しかけて来た客を食べるために歯を研ぎに駆け出した。その間、イワンは借りた三本のラッパを低く、少し高く、うんと高く吹き鳴らした。たちまち四方からあらゆる鳥が集まり、火の鳥が飛んできた。
「さあ、私の背中に乗りなさい。あなたの望む方向へ飛びましょう。さもないとババ・ヤガーに食べられてしまうでしょう」
駆け戻ってきたババ・ヤガーに尾羽根を引きちぎられたが、火の鳥はイワンを乗せて舞い上がった。長いこと飛んで、とうとう広い海に着いた。
「さあ、商人の子イワンよ、この世の果てはこの海の向こうです。ですが私はそこまで運んであげることが出来ません。自分で何とか工夫してください」
イワンは火の鳥から下り、礼を言って海岸を海に沿って歩きだした。すると小屋があり、入ると老婆が出迎えた。老婆はイワンにたらふく飲み食いさせてから、何をしに来たのかと尋ねた。イワンが一部始終を話すと老婆は言った。
「それはまあ。でもあの娘はもうお前を愛していないよ。お前に出会おうものなら引き裂いてしまうだろうさ。というのも、あの娘の愛の心は遠い場所に隠されているからね」
「どうしたらそれを取り戻せるだろう」
「少し待つがいい。あの処女王の所に私の娘が住みこんでいて、今日、私を訪ねてくるはずなのさ。何か聞き出せるかもしれない」
老婆はすぐにイワンを留針に変え、壁に刺した。
夕方になって老婆の娘が飛んで来た。老婆が処女王の愛の心の隠し場所を訊ねると「知らないわ」と言ったものの、処女王から聞き出してくることを約束した。あくる日、娘はまた飛んできて、母親にこう言った。
「大海原の向こう岸に一本の樫の木が立っていて、その中に箱があり、箱の中に兎がいて、兎の中に鴨がいて、鴨の中に卵があります。その卵の中に処女王の愛があるのです」
イワンはパンを持ってその場所へ行き、鴨の卵を手に入れると老婆の家に戻った。
やがて老婆の守護聖人の命日を記念した祝日が来て、老婆はパーティーを開いて処女王たちを招いた。正午かっきりに処女王と三十人の娘たちが飛んできてテーブルにつき、食事を始めた。最後にオーブンで焼いた卵が出されたが、処女王の前に置かれたものは例の鴨の卵だった。
その卵を食べ終えると、処女王は急にイワンが恋しくてたまらなくなった。すかさず、老婆は晴れ着を着せて隠しておいたイワンを連れて来た。二人は再会の喜びに浸り、陽気な宴はいつまでも続いた。
やがてイワンは処女王と共に彼女の国へ行き、結婚式を挙げていつまでも幸せに暮らした。
参考文献
『ロシア民話集(下)』 アファナーシエフ著 中村喜和編訳 岩波文庫 1987.
※明言されていないが、《飛んでくる》という処女王たちは自在に飛翔する神霊であり、羽衣をまとう天女であり、鳥の姿でこの世とあの世を行き来する女神なのだろう。
小さな舟で沖に漁に出ると、異界から美女が現れて「以前から好きでした、あなたに逢うために来たので結婚して」と誘いかけるという導入部は、『丹後国風土記』版の「浦島子」と共通している。
人食い女が訪問した男を食い殺すために歯を研ぎに出かけ、その間に男は楽器を演奏して逃げ出す…というくだりは[妹は鬼]話群と共通している。
隠されていた処女王の愛の心は、彼女の魂であると同時に生前の記憶でもあろう。世界の果てとは即ち冥界だ。かぐや姫が昇天して不死の天女に戻ると、両親や帝への愛の心がすっかり失われてしまったように、冥界の住人になった処女王は生前の心を失っていたわけだ。
参考 --> 「恋に溺れた継母」「二文のヤニック」【心臓のない巨人】
この「処女王」やインドの「ラール大王と二人のあどけない姫」のように、冥界神〜人食い鬼の家を訪ねると、母神が訪問者を針に変えて壁に刺したり、虫に変えて針で壁に留めるというモチーフがある。刺されている間は身動きもできないが、抜くと元の姿に戻る。虫が霊魂の暗示であることは明らかで、つまり針で魂を刺して留めている。
漫画で見られる《忍術・影縛り》のように、影に針を刺されると身動きできなくなる、影に針を刺して相手を呪うという俗信がある。一般に、影は霊魂と同一視されるものだ。針には何か、魂そのものに刺さって動けなくする呪力があるということだろうか。蝋人形に針を刺したり藁人形に五寸釘を打つ呪詛も知られているが、同じ観念が根底にあるかもしれない。
それが装着されている間は死んでおり、外れると生き返る。【白雪姫】話群にはそうした効果を持つ呪具が、針以外にも幾つも出てくる。お馴染みの毒リンゴが属する《死の果実(菓子)》が最も有名だが、他にも《死の指輪》、《死の衣服》がある。
指輪は、指に装着するという点で、眠り姫たちの指先に刺さった棘や針ととてもよく似ている。それを引き抜くと彼女は死の眠りから覚めるのだ。基本的に母からの贈り物として現れることは、母権の継承を思わせもする。
なお、眠り姫から指輪(腕輪)を抜き取る、というモチーフ自体は【眠り姫】話群でも見られるが、【白雪姫】話群とは効果も意味合いも全く異なっている。こちらでは、所有の証として王子がそれを持ち去るのである。帯(ベルト)を持ち去る場合もある。これに関しては次項で述べる。
次に、衣服について。「ヴォルスンガ・サガ」で、シグルズが眠るシグルドリーヴァ(ブリュンヒルデ)を発見したとき、彼女は全身に鎧をまとっており、肌に食い込んでいたそれを切り裂くことで目覚めた。(彼女は《眠りの茨》で刺されて眠っていたと説明されるが、棘を抜くような描写はない。)同じように、グリムの「腕ききの狩人」(KHM111)でも、湖の向こうの犬が番をしている高い塔に忍び込むと姫が眠っており、彼女は自分の肌着に縫いこまれたようになっている。狩人はそれを切り裂いてスカーフの一部を持ち去る。後に目覚めた姫はこれを手がかりに狩人と結婚する。また、死の眠りをもたらした衣服を脱がせると目覚めるというモチーフは、【白雪姫】話群では多く見られる。
シグルズが眠る娘の鎧を切り裂いた行為に、性的なニュアンスを読み取るのは容易だろう。実際、「太陽と月とターリア」や[命の水]話群の眠り姫たちは、眠っている間に妊娠までさせられている。尤も、「腕ききの狩人」では「肌着を切り裂いても姫の体には触れなかった」と強いて書き添えられていたり、【白雪姫】話群では服を脱がせるのは王子の身内の女性(母/姉妹/メイド)とされているのだが、これは道徳的配慮による変更・隠蔽だとみなすことも可能ではある。眠り姫は結婚(性的成熟)によって目覚めた、という解釈の人気が高いのは、こうした部分があるからに違いない。
しかし、別の観点からの解釈もできるのではないか。
『千夜一夜物語』版類話では、模擬的に葬られた王子を包む七重の屍衣を、かつて眠り姫だったシットゥカーンが一枚一枚開いていく。全て開き終わると彼は目覚め、忘れ去っていたシットゥカーンへの愛を思い出すのだ。七重の屍衣からは、メソポタミア近辺にあった《七層の世界》の観念……冥界(天国)へ向かうには七つの門を通らねばならないという信仰が感じられる。シュメールの女神イナンナは、冥界へ下る際に七つの門を通り、門ごとに身につけていた衣服や装飾品を取り上げられて、最後には裸になった。「太陽と月とターリア」で王妃に処刑されそうになったターリアが一枚ずつ身につけていたものを脱いでいくシーンにもこの信仰の片鱗が感じられる。つまり、一枚ずつ服を脱ぐ行為には《少しずつ死に近づく》、あるいは《死の世界から少しずつ戻ってくる》という意味が読み取れる。
ターリアの服を脱がせ死の世界に送ろうとする王妃には、冥界の母神のイメージも感じられる。【白雪姫】話群で服を脱がせて娘を死の眠りから呼び覚ますのが王子の母や姉妹…女性であることとも、どこかで繋げられるかもしれない。
そう考えれば、死の眠りについた者の衣服を脱がせたり装飾品を外すと、目覚め蘇ることにも、共通した意味を感じ取れはしないだろうか。
現代の子供向けアニメーションでも、魔法少女が変身する際には一瞬なりとも素裸かそれに近い姿に描かれがちであるものだ。赤ん坊が産まれる時には素裸であるように、あの世からこの世へ、あるいはこの世からあの世へ転生する際には、人は服や装身具といった虚飾を捨て去り、無垢な魂のみになるものだという観念が、人々の意識の底にあるのではないだろうか。
「ヴォルスンガ・サガ」において、シグルズは持っていたアンドヴァリの黄金の中から腕輪を、ブリュンヒルデに二度も与えている。一度はシグルズとして愛を誓うために。もう一度はグンナルの代理人として、婚姻の証に。
物語上、腕輪がエンゲージリングを意味していることは確かであるが、これが幸福な結末を生むことは、まずない。疑念と誤解を呼ぶ火種になってしまう。
シグルズはグンナルとして腕輪を与えた際、以前自分が与えた方の腕輪を持ち去った。これが原因となって後にブリュンヒルデたちに殺されることになった。イギリスを発祥とする聖杯探索伝説話群では、天幕の中で眠る美しい乙女を発見した愚かな王子ペレドゥル(パーシヴァル)が無法にもキスをする。目を覚ました彼女に食料を提供させ、たらふく飲み食いしてから記念に彼女の腕輪(または指輪)を持ち去ったが、実はそれは彼女の夫からの贈り物だったため、彼女は夫にひどい虐待を受けることになった。シェイクスピアの劇「シンベリーン」では、妻の貞節を試すべく、夫が知人に妻を誘惑させる賭けをする。妻はまるでなびかなかったが、このままでは賭けに負けると思った知人は荷物に潜んで妻の寝室に侵入し、ぐっすり眠る彼女の寝姿を観察した上に夫からの贈り物の腕輪を抜き取って持ち去った。腕輪を見せられた夫は妻が裏切ったのだと思い込み、殺そうとする。
どうして、(黄金の)腕輪は不和を呼んでしまうのだろうか。
ワーグナーの歌劇「ニーベルンゲンの指輪」では、黄金の指輪には「所持者は指輪に縛られ、全てを得るが全てを失う」という呪いが掛かっていることになっている。その呪い通り、全て……主人公たるジークフリートとブリュンヒルデの二人も、ギービヒの一族も、神々の世界そのものすらもが終焉を迎える。権力と破滅をもたらす畏るべき指輪の設定はトールキンの小説『指輪物語』に引かれたこともあって非常に有名だが、引きずられないよう注意しておかねばなるまい。伝承の原形に近いと思われる「ヴォルスンガ・サガ」でも、確かに本来の黄金の持ち主であった小人アンドヴァリが呪いの言葉を吐いてはいる。だがそれは「その黄金と腕輪を持つ者は、誰でもそのために命を落とすことになる」というものだ。それで全てを得られるとは言っていないし、「全てを失う」という広義の表現もしていない。ただ、所持者は死ぬとだけ言っている。
黄金の本来の所持者たる小人の王は、昏い世界(地下/洞穴/開く岩壁の向こう/霧の国)に住んでいる。現在この小人のキャラクター化は進んで、《地下から黄金や宝石を採掘し、優れた鍛冶師でもあって呪宝を作り上げる、背が低く髭を垂らした》 亜人種なのだと認識されがちだ。一方、歴史的見地から伝承を《合理的に》解釈しようとする研究者は、彼らは征服者から逃げて洞窟に隠れ住んでいた小柄な原住民族だと唱えることもある。亜人とまではいかずとも、やはり一種の異人種と見ている。だが、そうなのか。確かに、異民族や漂泊者を見て魔物を想起した者もいたかもしれない。だがそう認識する意識の中には、既に《小柄で、暗い所にいて、黄金を授けてくれる》モノへの観念、信仰が存在していたのではないか。
日本には竹筒に入るほど小さな狐(管狐)や、それに類似した影のような小人の伝承があるが、これは血筋に取り憑く霊物とされる。黄金の所有者たる地下の王が小人とされるのも同じことで、彼らも冥界神〜神霊であり、《小さい=見えづらい=神霊》という暗示があるのではないだろうか。現に「ニーベルンゲンの歌」の黄金の番人・小人アルプリヒも、「不死身のザイフリート」の小人オイゲルも、姿を消すことのできる呪宝・隠れマントを持っており、彼らは自在に姿を消せる〜見えづらいと認識されていたことが窺える。同じ呪宝は韓国ではトッケビの帽子、日本では天狗の隠れ蓑、隠れ頭巾(笠)などと言われ、いずれも魔物(神霊)が持っているものとされている。古代日本では鬼(魔物〜神霊)は蓑笠を身につけて姿や顔を隠しているものとされていた。(だから清少納言は『枕草子』で、蓑虫は鬼の捨て子だと書いている。)というのも、「鬼=霊=姿が見えない」という観念があったからである。自在に姿を消して《神出鬼没に》活動する、それは霊の特質だ。だからこそギリシアの伝承では、霊の王たる冥王ハデスが隠れ兜の所持者であることになっている。
オーノワ夫人の「爛漫の姫君」では、姫君は両親の持っていた《(一撃必死の)宝剣》、《自在に姿を消せる、紅玉が眩く輝く宝冠》を盗んでいく。これらの呪宝が冥界の力を暗示しているのは明らかだ。特に宝冠は、自在に姿を消せるという点で[ニーベルンゲン伝説]の隠れマント(兜)と同じものだし、頭や首で眩く輝く宝石は、「小さな太陽の娘」や「バタウン」を参照するに、冥界からの出現者(太陽の化身)が身につけている定番の装飾である。
ギリシアの伝承によれば、クレタ島のミノタウロスの迷宮に英雄テセウスが臨んだとき、一説によれば王女アリアドネが授けた、宝石をちりばめた黄金の冠の光で螺旋状の迷宮を照らして進んだとされる。迷宮は冥界を暗示している。それを照らす宝冠は日月の光を象徴すると同時に、冥界を支配する冥王の力を示している。アリアドネは太陽神ヘリオスの孫娘であり、ディオニュソス神の妻であったとされる。例の宝冠も、元々ディオニュソスがアリアドネに贈ったものだと。デュオニソス神は一般には天神ゼウスの息子とされるけれども、《冥界でのゼウス、犠牲死と復活の神》という側面も持っていた。つまりアリアドネは冥王の妻、冥界の女王神の一形態とみなせる。アリアドネの名の意味は「聖なる、清い」で、ディオニュソスの妻としての別名アリデラは「遠くから明るく見える女」という意味である。
なお、私見ではあるが、《日月光〜霊力》を象徴する頭または首の宝石は、西欧の《雄鶏の石》、東洋の《竜の如意宝珠》の伝承と、恐らく根を同じくしている。仏教の仏天やキリスト教の聖人などの背後や頭上に描かれる光背、いわゆる《天使の輪》も、もしかしたら繋がっているかもしれない。
黄金の所有者たる小人が神霊〜冥界神であると前提すれば、その財宝が黄金または輝く宝石であることに、また別の意味が見えてくる。説話には光り輝くものがしばしば現れてくる。金銀財宝、黄金(青銅/水晶)の館、黄金(水晶)の橋、黄金(青銅)の門、黄金の鳥、黄金の魚、黄金の果実、黄金の枝、黄金(青銅)のサンダル、黄金の髪の冥界帰りの英雄、黄金の髪の大地の乙女……。結論から言えば、説話における黄金(光輝)は太陽を象徴しており、それが神に関わるものだというサインになっている。そして太陽神と冥界神は表裏一体で、観念上、同一の存在として扱われる。神は幸(生命)を与えもするし奪いもする存在だからである。冥界は血と炎と暗黒に包まれた恐ろしい地獄だと語られる一方で、光輝と黄金の中にたゆたう極楽だとも語られる。両極端でもあるこの二つのイメージは、殆ど同じ世界について語っている。
つまり、小人が黄金や宝石を持っているのは、彼らが地下でそれを採掘しているからではない。神霊である彼らが太陽神でもあり、輝く霊力…豊穣の力を持っていることを表しているのだ。ギリシアの伝承で、女神が黄金のリンゴを持っていると語られることと根は同じである。だが古い信仰が廃れるにつれて意味が忘れ去られ、合理的に説明しようとして「小人は地下で鉱石を掘って細工をしている」などと言われるようになったのだろう。
「ヴォルスンガ・サガ」で小人の王アンドヴァリが黄金を要求されたとき、彼は腕輪だけは渡すまいとしていた。実は、この腕輪があれば幾らでも新たに黄金を生み出すことができたからだ。そう。この黄金の腕輪は、日本の伝承で言うところの《打出の小槌》と同じものだ。北欧の『トルストンのサガ』にも、小人が贈ってくれた、はめていれば金に不自由しない指輪が出てくる。
しかし冥界の呪宝がどんな形をしていてどんな幸を与えてくれるかは語り手の裁量であり、一律化はしていない。冥界から授けられる指輪には、はめると姿を消せるもの、逆に姿を消したモノが見えるようになるもの、剛力になるものなど、様々な機能のものがある。
[ニーベルンゲン伝説]において、どうして小人(もしくはニーベルング族)の黄金は所持者に死をもたらすとされるのか。それは、それが冥界から…死の世界からもたらされたものだからに他ならない。神に祝福され同一化するということは、この世での死を意味するとも解釈できるからである。
アイルランドの「フェヴァルの息子ブランの航海」によれば、王子プランの前に美しい乙女が現れて銀のリンゴの花枝を渡し、エヴナの国へ来るように誘う。浦島太郎が常世に去ったように、エヴナの国で暮らしたブランは人間とは異なる時間を生きることになり、二度と人界には戻らなかったとされる。つまり、女神から愛の証として冥界の宝を渡され、神の国の一員となって、人間としては死んだのであった。
シグルズは愛の証としてブリュンヒルデに黄金の腕輪を贈った。ディオニュソス神がアリアドネに黄金の冠を贈ったように。しかし後に、ブリュンヒルデは腕輪を新たに現れた英雄グンナル(に化けて現れた、記憶のないシグルズ)に取られてしまい、それが後の不和と死を呼ぶことになる。シグルズは死に、ブリュンヒルデも火で焼かれて死んだ。一方アリアドネも、宝冠を英雄テセウスに与えてしまう。よく知られている話では、アリアドネはその後テセウスに置き去られ捨てられたとしか語られないが、別説によれば自ら縊死した、産褥死した、ディオニュソスが月女神アルテミスを唆してアリアドネを月神の矢で射らせ、火で焼かせたなどとする。
『エッダ』によれば、ブリュンヒルデは死後に戦乙女となって冥界へシグルズを迎えに行ったという。アリアドネも、一説によればディオニュソスと共に車に乗って昇天したとされる。神として結婚し、その意味ではハッピーエンドを迎えている。
黄金…冥界の力を入手する、冥界と繋がるということを、結婚という形で表す。冥界と繋がり冥界神と一体化することは、この世での死を意味する。よって、冥界の黄金でエンゲージされた結婚は、《死》というこの世でのバッドエンドを迎えるのだろう。
さて、【眠り姫】話群において腕輪(指輪)に近い機能を与えられている小道具に、帯(ベルト)がある。チェコの「命の水」では、王子は眠る女王と愛の床を共にした後、彼女の銀の帯を持ち去っている。グリムの「腕ききの狩人」ではスカーフだ。対して「ニーベルンゲンの歌」では、ジーフリトがグンテルの身代わりとしてプリュンヒルトの処女を奪った際、彼女から黄金の指輪と宝石を散りばめた絹の帯の二つを奪っている。
帯を解くことと服を脱ぐことはほぼ同義にイメージ出来るので、艶めいた印象を抱きやすい。だが、それだけで思考停止してしまうのは尚早だろう。帯には冥界の呪宝としての意味もあるらしく思われるからである。
十三世紀ドイツの『古英雄叙事詩集』に収められているベルン王ディートリッヒ(ティードレク)関連の詩の中に、小人王ラウリンの物語がある。
チロルの山中洞穴に小人たちの王ラウリンが住み、その洞穴は宝石で輝き、絹糸で囲った彼のバラ園を荒らす者の手足を切ってしまう。魔術を操る彼は誰にも負けたことがない。そんな噂を部下のヒルデブラントから聞いたディートリッヒは、名を上げるべく部下と共に出かけ、バラ園をわざと踏み荒らす。現れたラウリンはノロ鹿ほどの馬に乗った小さな人物であったが、馬勒は宝石で輝き、黄金の鎧には竜の血が塗りこめられて刃が通らず、黄金の兜には赤い宝石が燃え、全身からは聖なる黄金の光輝が放たれていた。まさに太陽神の姿である。説話の世界では手足の欠損は《死…冥界下り》の比喩だが、ラウリンはディートリッヒたちの左足と右手を切り落とそうとする。
姿を隠す魔法のマントをまとったラウリンにディートリッヒは苦戦したが、ついにマントを奪って彼を無力化することに成功する。力を奪われた瞬間、ラウリンは長く叫ぶ。敗北したラウリンはディートリッヒたちを自分の洞窟に招いて忠誠を誓い、歓待したが、こっそりと、十二人分の力を授かる魔法の指輪と、やはり十二人分の力を授かる魔法の腰帯を装備し、力を取り戻した。そしてディートリッヒたちに睡眠薬を飲ませて地下の穴倉に投げ込んだのである。
しかしラウリンに囚われて妻にされていた乙女キューンヒルトが、こっそり魔法の指輪を授けて救った。アリアドネがテセウスに宝冠を与えて夫のディオニュソス(と、兄・ミノタウロス)を裏切ったように。この指輪をはめるとマントで姿を隠した小人を視ることが出来るようになるのだ。
ラウリンは大変な強敵であったが、ディートリッヒはヒルデブラントの助言によって、指輪をはめていたラウリンの人差し指を落とし、腰帯をもぎ取った。力を失ったラウリンは再び敗北し、キューンヒルトのとりなしで命ばかりは助けられたが、洞穴の財宝は全て奪われ、彼自身は捕虜にされて晒し者になった。それ以来、小人たちは洞穴の奥で鍛冶仕事をさせられているのだという。
以上の物語では、帯を奪われるのは女性ではない。しかし帯や指輪が剛力の源で、奪われると力が失われてしまうという状況は、「ニーベルンゲンの歌」のプリュンヒルトが並の男では太刀打ちできない剛腕の持ち主で、初夜の床で夫のグンテルを拒絶して縛り上げるが、代理人のジーフリトが押し倒して初夜を済ませ指輪と帯を奪うと、それ以降は力を失ってただの女になってしまったと語られる点に似てはいないだろうか。
黄金の腕輪(指輪)や宝石できらめく帯が太陽神〜冥王の力の象徴ならば、それを奪われるということは、神が力を失う、ということでもあったに違いない。
ギリシア神話の英雄ヘラクレスの十二功業の一つに、女戦士の女王ヒッポリュテの帯を奪うというものがある。ヒッポリュテはヘラクレスを歓迎して(一説には彼に子種を貰うことを条件に、愛の証として)自ら帯を渡そうとしたが、(女王神ヘラの策謀により)女王をさらわれると思い込んだ部下たちが武装して港に押しかけ、それを見たヘラクレスは騙されたと思ってヒッポリュテを殺して帯を奪い取った。これだけでも悲しいすれ違いの物語だが、更に悲しいことには、ヘラクレスは帯を王女アドメテの依頼で求めに来たのであった。ジーフリトが勇猛な女戦士であったブリュンヒルデからベルトを奪って妻クリームヒルトに与えたように、別の女に与えるためだったのだ。
この帯はヒッポリュテの父である軍神アレスの授けたもので、女王が最も勇敢である印であり、《力》の象徴であった。物語上、女王を殺して帯を奪っているが、観念的には帯を奪われたために女王は死んだ…力を失った、ということなのだろう。
ギリシア神話中のアマゾニス(アマゾン)は、北アフリカ、アナトリア、黒海地域に住んでいた実在の母系部族をモデルにしていると考えられている。彼らは女神を崇拝し、また、馬を飼いならして強力な騎馬部隊を所持していた。ヘラクレスに帯を奪われ殺されたアマゾニスの女王・ヒッポリュテの名は、《奔放な雌馬》を意味している。
ところで、ノルウェーの「ティードレクス・サガ」においてジグルトに神馬グラーネを与えたのは、女王ブリュンヒルトであった。ジグルトは彼女の城の門を蹴破って中に入るが、ヒッポリュテがヘラクレスを歓迎したように、ブリュンヒルトはジグルトを歓待する。
一方、ロシア民話「若返りのリンゴと命の水」にも、こんな一節がある。
イワン王子は自分に合った馬を選ぶことが出来ず、しょんぼりして歩き始めました。すると、向こうから《人目を忍んで暮らしている》お婆さんがやって来ました。
「こんにちは、イワン王子。何をそんなに悲しそうにしているんですか?」
「だって、お婆さん、悲しまないではいられないよ。いい馬を選べないんだ」
「最初から私に頼めばよかったのに。いい馬は穴倉に鉄の鎖で繋がれていますよ。それを連れ出せたなら、あなたのいい馬になるでしょう」
イワン王子は穴倉に行くと、鉄の扉を蹴り飛ばしました。中に飛び込むと、馬は前足を王子の両肩に乗せてきました。王子がそのまま怯みもせずにいると、馬は鉄の鎖を引き千切って穴倉から外に躍り出し、イワン王子を引っ張り上げました。
馬がいる鉄門で閉ざされた穴倉が冥界の暗示であり、鉄門を蹴破ることが冥界への侵入を意味し、そこへ導く「人目を忍んで暮らしているお婆さん」が冥界神であることは、容易く読み解けるだろう。
説話においては、馬はしばしば死者〜神霊からもたらされる。例えばロシアの「魔法の馬」では、父の亡霊が墓から起き上がって神馬を呼び、息子に授ける。日本の「灰坊太郎」では母の亡霊が神馬を授けている。ハンガリーの「天まで届く木」やアラブの「もの言う馬」、日本の「麒麟にさらわれた子供」のように、冥界神の家で神馬を発見して味方にすることも多い。どういうわけか、馬は冥界〜死者と関連するらしい。
特に北欧の人々にとって、馬は勇者の葬儀には欠かせないものだった。死者は馬に乗ってあの世へいくと考えられていたからだ。馬の鐙には長靴が反対方向に取り付けられた。というのも、この世のものとあの世のものは鏡像のように逆なので、死者のかかとは反対を向いていると考えられていたからである。中世日本の説経「小栗判官」の照手姫の鷹の夢には、冥土へ去る小栗が逆鐙に逆鞍で馬に乗って葬列と共に北へ去っていく、という情景が出てくるが、同じ観念であろう。ギリシアの伝承でも、冥王の別名に《クリュトポロス(馬で名高い者)》というものがあり、古い墓に納められていた壺には、英雄のために荘厳な馬具のつけられた葬式馬車が描かれている。
古い時代では馬は死者とともに墓に葬られることがあった。ケルトの女神エポナは雌馬であり、死者を速やかに冥界に運ぶ馬であり、恐らくは冥界で転生させる女神として、スペインやローマにもその信仰は広まっていた。
死者は馬と関わり、その馬は多くの場合雌馬であるか、女神から授けられる。死と関わる馬は、時に人を食らう怪物として語られる。
ギリシアの地母神デメテルは、切り刻まれ調理されて食卓に出された幼い王子ペロプスの肩の肉を食べてしまったと伝えられている。彼女は他の神々と共に、ペロプスの残りの肉を大鍋で煮込んで引き出し、蘇らせた。再生したペロプスは以前より美しく立派になり、特にデメテルが食べた肩は象牙で補填され、白く輝いていたという。この特徴は彼の子孫の誇りとなった。女神デメテルは雌馬に変身して冥界女王ベルセポネと神馬アリオンを産んだという神話をも持つ。
王子ペロプスは成長して後、王女ヒッポダメイア(馬を御する女、の意)に求婚した。だが、彼女を得るためには彼女の父オイノマオスと馬に牽かせた戦車で競争せねばならず、それまで多くの若者が挑戦していたが、みんな敗北して、その首はオイノマオス王の宮殿の入り口に釘づけにされて晒されていた。というのも、オイノマオス王はアレス神より授かった二頭の雌馬を持っており、その足が恐ろしく速かったからだ。……ペロプスはオイノマオス王を殺し、ヒッポダメイアと結婚した。しかし後に、ヒッポダメイアは息子(一説には継子とされる)を憎んで殺し、国を追われ、死後に骨または灰が神殿に祀られたという。
ロシアやジプシーの民話の中では、馬は煮え立つ大釜に入れられる若者の援助者としてしばしば現れる。釜の中で煮え立っているものを馬のミルクだと語ることもある。死と再生、冥界の女神、女神が食べること、そして馬(特に雌馬)は関連付けられている。
冥界神的な人物が飼っている人食い馬の伝承は、様々な英雄伝説に見られる。「小栗判官」で、照手姫の父が婿・小栗に与えた難題は、人食い馬の鬼鹿毛を乗り慣らすことであった。この馬は頑丈な横木と鉄柵の中に入れられ、四方八つの鎖で繋がれていた。また、伝説によればアレクサンドロス三世の乗馬・ブケパロスは人食い馬であり、乗りこなす者は世界を支配すると預言されていた。ギリシア神話では、トラキア王ディオメデスが四頭の人食いの雌馬を鉄の鎖で青銅(黄金)の飼葉桶に繋いで飼っていた。この飼葉桶には切り刻まれた人間の死体が入れられた。ヘラクレスがディオメデスを捕らえて食わせたところ、雌馬たちは大人しくなったという。
人間を貪り食う、または踏み潰す雌馬。これが《死》そのもの、そして冥界の女神自身を暗示していることは明らかである。死とは女神に呑まれて胎内に回帰することであり、女神は内部に空洞〜子宮を持つ全てになぞらえられた。大きな鍋とも、燃えるかまどとも、深い洞穴とも、人食い鬼とも、人食い竜とも、人食い狼とも、人食い獅子とも、人食い牛とも、人食い馬ともみなされていたのだ。冥界女神と獣を同一視するのは、神霊は獣の姿を取るという観念の影響もあっただろう。霊の女王/母である彼女自身も獣の姿を取ることができる。
ロシアの「魔法の馬」には、若者イワンが亡父に授かった馬の、耳の穴を潜って美々しく変身するシーンがある。耳の穴は、口とも膣とも言い換えて構わない。これは人食い馬に食べられることと同じであり、女神の胎の中に入ること、即ち冥界下りの暗示である。
ところで、イワンの魔法の馬は鼻から火を吹き耳から煙を吹いている。ギリシアの英雄イアソンも、金羊皮を得るために鼻から火を吹く凶暴な雄牛を従える難題をクリアしなければならなかったが、どうしてこれら冥界に属する牛馬の鼻からは火が吹き出るのだろうか。
思うにこれは、それら牛馬の腹の中が冥界と同一であり、地獄の炎が燃えていることを意味しているのではないか。そう考えてみれば、西欧の説話に登場する龍がしばしば口から炎を吐くことも、無関係ではないと思えてくる。
冥界神が自身の力の象徴たる腕輪や帯などの呪宝を奪われたとき、力を失い、無力な存在になり下がる。事実、「ニーベルンゲンの歌」のプリュンヒルトは、元は並の男では敵わぬ剛力を発揮する女戦士だったものが、腕輪と帯を奪われて以来、ただの女になってしまったと語られている。
ただ、ここで彼女が奪われたのは呪具だけではない。彼女は純潔を奪われ、その証として腕輪と帯をも持ち去られたのだ。ここには、女は性的に男に支配される(性的に屈服させれば女は脅威ではなくなる?)という観念もが同時に含まされている。
ギリシア神話によれば、トロヤ戦争にアマゾニスが参戦し、英雄アキレスがアマゾニスの女王ペンテシレイアを殺した。ホメロスは、アキレスが死の間際の女王を見てその美しさに恋をしたと悲恋を語っている。絵画にも、アキレウスが横たわる女王を抱きかかえて兜を脱がせ、じっと見入っている様子などが好んで描かれた。だがバーバラ・ウォーカーの『神話・伝承事典』には、アキレスは女王の死体を死姦したのだという解釈が書かれてある。しかもそれを行ったのは女王に恋をしたからではない。アマゾニスの亡霊の祟りを逃れるための呪いであったというのだ。
女が恐るべき力を持っており、(意識的にか、無意識的にか)初夜の床で夫を殺そうとする。こうした観念を滲ませる民話群があるのは確かだ。
グンテルがプリュンヒルトを得るべくジーフリトの助力を得たように、若者が《旅の仲間(従者/友人)》の助力を得て強力な女王を妻にする。そして類話によっては、《旅の仲間》は初夜の床にすら入ってくる。ジーフリトがグンテルの代わりに寝室でプリュンヒルトを屈服させたように。
死人の借金を払った男 クロアチア
一人の若者が父親にせがんで許可をもらい、百ドゥカーテン金貨を持って、商売を始めるために家を出た。すると途中で、二人の男が墓から男の死体を引きずり出して、罵りながら革鞭で打っているのに出くわした。なんでも、この男は二人から借りた百ドゥカーテンを返さないまま死んだのだと言う。若者は自分の百ドゥカーテンを与え、死人を墓に戻させてやった。
おかげで手ぶらで家に帰って父親に叱られることになったが、若者は再び商売の元手をせがんだ。父親はリンゴを一つ渡してこう言い聞かせた。
「それじゃ行ってこい。お前と一緒に商売をしてくれる人を探すんだ。一緒に商売しに行くと言う人がいたら、このリンゴをやって、お前たち二人で食べられるように四つ割りに切ってもらえ。そしたら私のところに戻ってきて、どうリンゴを分けたか教えなさい」
最初に出会った男は、四つ割りのリンゴの三切れを自分のものにして、若者には一切れしかよこさなかった。父親はそれを聞くと「お前のためにはなならん人間だ、別の相棒を探せ」と言い、またリンゴを一つくれて送り出した。二人目の男は半分くれたが、父親はその男も駄目だと言った。三番目の男は、若者に三切れくれて、自分は一切れしか取らなかった。父親は満足し、息子に百ドゥカーテン渡して送り出した。
若者と男は別の皇帝の国へ行って商売をした。皇帝の宮殿の前を通りかかると、窓にそれは美しい皇帝の娘の姿が見えた。すると男が「あの人と結婚したいかね?」と若者に訊いた。「皇帝のご息女と結婚したくない者がいるものか!」と若者は答えた。
夕方に宿に落ち着くと、男は皇帝の所に結婚の申し込みに行くようにと若者に言った。「俺みたいな者が、どうしてそんなこと出来るものか」と言えば、「行って申し込めば許してくれる。ただし、一度ここに戻って、何と言われたか俺に報告するんだ」と言う。
若者が皇帝の宮殿に行って求婚すると、なんと、すぐに聞き届けられた。ただし、今夜すぐにご息女と同じ寝室で過ごすように、と。若者は宿に戻って相棒に報告した。男は「よし、さあ行ってこい」と若者を送り出したが、その後で自分も宮殿に行って、皇帝の娘の寝室に入って二人の様子を見張っていた。
夜中に、皇帝の娘が身体を揺すった。すると体の中から竜が現れて若者を呑み込もうとした。男はすかさずその首を斬り落とした。胴体は娘の体の中に戻ってしまったが首は残り、男はそれを布に包んで宿に帰った。
朝になり、若者が娘と共に朝を迎えたことが知れると、城中が喜び、大砲は歓喜と共に撃ち鳴らされた。というのも、今まで多くの男が娘と共寝したが、一人も朝を迎えることがなかったからだ。
皇帝は娘婿に、自分の宮殿の隣にもう一つ宮殿を建ててやろうと約束した。しかし若者はすぐに応諾せず、相棒の所に行って相談した。すると彼は「ここには絶対住むんじゃない。ただ、あの娘と、ラバを三十頭、シャベルを三十丁貰うがいい。後は何も貰わん方がいい。娘の持参金など欲しがるな」と言うのだった。
皇帝はしきりに引きとめたが、若者の意思が固いと見てとると、要求どおりにしてくれた。若者は妻と相棒と共に、故郷への長い道を辿り始めた。
やがて小さな円くなった谷に入ったとき、男が「お前の幸運は地面の中にある」と言い出して、シャベルでここを掘るように促した。掘りに掘ると宝物庫が口を開いた。若者は財宝を幾つもの袋いっぱいに詰めてラバに積んだ。
ついに若者の生国に入った。すると相棒が「兄弟、それじゃ分け前をもらおうじゃないか。俺とお前はここで西と東に別れるんだからな」と言った。もうけた全てを半分に分けることになったが、なんと、皇帝の娘まで半分にすると言う。
「彼女は分けられないぞ。そんなことをしたらお前も俺も、誰も彼女を持てないじゃないか」
「いや、どうしても分けるんだ。もうけは山分けだと決めておいただろう。お前は娘のこっちの手を持て。俺はこっちを持つ。そうすりゃスッパリ分けられるからな」
そう言うと、男は半月刀を振り上げた。娘が悲鳴をあげかけたとき、彼女の中から首のない竜の胴体が跳び出した。
竜が抜けてしまうと、男は布に包んでいた竜の首を取り出して見せて、初夜の晩の出来事を打ち明けた。若者は男に感謝し、彼がもう娘を斬り分ける気がないことを喜んだ。
「ここでお前は東に、俺は西に別れよう。俺は宝は要らない。娘も要らない。俺は死人だからだ。お前が百ドゥカーテン出して葬ってくれた、あの死人なのだよ」
言い終わると男は土に還った。一方、若者は娘を連れて父親の家に帰り、親子夫婦で共に暮らした。
参考文献
『世界の民話 アルバニア・クロアチア』 小沢俊夫/飯豊道男編訳 株式会社ぎょうせい 1978.
参考 --> 「命の水」「忠臣ヨハネス」「縛り首による死の回避」
初夜の床に現れた蛇は、どこから現れたのだろうか。ロシアの類話では、相棒の男は実際に王女を真っ二つに切り裂いている。すると中から小蛇がごっそり出たので、これを全て退治して内臓を奇麗に洗い、水を注ぐと、王女は以前より美しくなって蘇った。つまり、蛇は娘の体内にいたのだ。更に、次に紹介するパプア・ニューギニアの伝承を参照すると、蛇が娘の体のどこから出て来ていたのかの見当もつく。
にしき蛇 パプア・ニューギニア 東セピク地方
昔、一人の男が子供を連れて森へ子守ネズミを捕りに行き、藪の中に倒れて朽ちたリンブムの木(シュロの一種)を見つけた。朽ちた穴の中に錦蛇の卵を見つけて持ち帰り、男の妻はそれをゆでたまごにして食べた。ところが、それ以来女の腹の中に蛇が宿ったのである。
妻の腹がどんどん膨れたので男は誰の子だと訝しんだが、妻は知らないと言う。ともあれ出産準備をせねばならないとて、女は煮炊きのための薪を作りに行った。そして枯れ木を細かく割っていると、中からウジ虫が這い出した。すると、女の女性器から錦蛇が滑り出してウジ虫を食べたのである。その間女の腹はしぼんでいたが、蛇が食べ終わって戻ると再び膨らんだ。これが何度も繰り返された。
女は夫に相談し、隠れて見張っていてくれと頼んだ。そこで男が木の根元に隠れて薪割りする妻の様子を見ていると、薪の中からウジ虫が這い出すなり、妻の足の間から錦蛇がするすると降りて来て、ウジ虫を食べ始めるではないか。男は小刀を手に忍び寄って、錦蛇の頭を切り落とした。すると頭は茂みの中に飛んで行って隠れ、胴体は再び妻の女性器から胎内に滑り込んで、そのまま出てこなくなった。
そんなわけで、女の女性器からは時々血が出るのである。そして子供は胎内の蛇から生じるのだと言う。
参考文献
『世界の民話 パプア・ニューギニア』 小沢俊夫/小川超編訳 株式会社ぎょうせい 1978.
日本の苧環型の蛇婿譚では、娘が蛇の化身の男と交わって子を身ごもる。薬湯を使って堕胎したが、死んだ小蛇がうじゃうじゃと大量に下ったと言う。ロシアの民話で、王女の中に小蛇がぎっしり詰まっていたこと、パプア・ニューギニアの伝承の錦蛇が、女が食べた卵から生じた…いわば宿った胎児であったことと、どことなく繋がりを感じる。
初夜の晩に現れた蛇は新郎を殺す。蛇はどうやら花嫁の女性器から現れるらしい。とくれば、どうやら性交時に男性器を噛まれて殺される、という、女の性への恐怖が根底にあるらしく思えてくる。
女性器は俗に《下の口》と呼ばれることがあるが、女性器に歯が生えていて、挿入された男性器を噛んで男を殺すという【有歯膣】の伝承は、台湾、日本、北米などに見られる。
●美しい娘が結婚するが、夫は一夜にして死ぬ。彼女の女性器には四本の歯があるのだ。これを知った母は娘を朱塗りの箱に入れて海か川に流す。流れ着いた娘を男たちが発見し、酔わせて歯を挟み切る。挟み切られた歯はトンボ玉になった。(あるいは、歯を砥石で磨り減らした。)
まずは竹の棒や犬などで試し、最後に人間の男が試す。何事もなく、娘は安全になったことが確認された。彼女は地元の頭目の妻になったという。(台湾 蕃族)
●北海道から海を隔てたところに女の集落という島があり、男はおらず、戦を好む女戦士たちだけが住んでいる。彼女たちの膣には歯があり、鹿の角のように秋に抜けて春に生える。最上徳内が行って短刀の鞘で試したところ、歯型が付いたという。女たちは鎖鎌で向かってきたが、逃げのびた。
沙流海岸に時々黄檗の皮が流れ着くのを、アイヌの人々は"メノココタンの浮"と呼ぶ。(アイヌ)
●五人の男がアザラシ漁に出た。船長は食人族に食われてしまい、残る四人は女だけの島に辿り着いた。女たちはもてなして泊めるが、危険だから変な気は起こさないように、と忠告する。しかし二人の男はそれを無視して女たちの寝床にもぐりこみ、陰歯に男根を噛み切られて死んだ。三人目の男は赤い砥石(または海岸で拾った白い石)を挿入し、歯を折ったので無事だった。女たちは喜び、生き残った二人の男を二人の死体と共に送り返したという。(アイヌ)
同じような伝承は日本の津軽や能登にもあり、木や黒銅製の物品を挿入して歯を砕いたと語る。その他、日本本土では「嫁の歯」という民話としても伝わっていて、こちらは既に笑話化されている。
●互いに《うぶ》な男女が結婚することになった。周囲の人は、女には「男の人のアレって、杵みたいに大きいのよ」と教え、男には「女のモノには歯が生えているんだぜ」と教えた。さて初夜の晩、二人は互いに教えてもらったことは本当なのかと疑い、男は膝で試そうと、女は指で確かめようとした。そして互いに「本当だった」と勘違いし、怖くなって、そのまま離婚してしまったという。(日本)
女に男性器を噛み切られる、というのは、男にとって潜在的な恐怖なのか。東南アジアや台湾などには、結婚直前の娘の前歯を抜いたり削ったりする風習があったそうだ。夫を傷つけないため、だそうである。
説話の中の王子は、素晴らしい花嫁を得るために《旅の仲間》の助力を仰ぐ。何故なら、初夜の床の花嫁は大変危険な存在だからだ。先に挙げた「死人の借金を払った男」のごとく蛇が襲ってくることもあるし、プリュンヒルトのように暴れることもある。ロシアの民話では、花嫁がずっしりと重い手を花婿の胸に乗せたり、首を締めあげたりして窒息死させようとすることも多い。《旅の仲間》は王子を護るために初夜の寝室に同席させてほしいと望む。あるいは「私をあなたの代わりにベッドで寝かせてくれ」とさえ懇願する。
こうして、花婿の身代わりとなった《旅の仲間》は襲ってきた怪物を倒し――同時に花嫁の《女》をも征服するのだ。彼は花嫁を壁に叩きつけたり、何本もの金属の捧でさんざんに殴りつけたりする。そうしてベッドの上に放り投げ、無抵抗にしてしまってから花婿に譲り渡す。この暴力は、女を無力にするという点で、陰歯を折る行為と同質のものかと思われる。
説話において、優れた援助者が身代わりに求婚の難題をこなすモチーフは珍しくはない。それでも、ジーフリトがグンテル王に代わって初夜までこなしてしまうくだりは、多くの読み手にとって奇異に感じられるものではないだろうか。初夜の契りを夫以外の男が行う。それも、夫公認で。一体これは何なのか?
実は、これに似た習俗が現実に存在していた。《初夜権》である。
初夜権とは、集団の上位の男――王/領主/長老/家長/仲人などが、花婿に代わって花嫁との初夜をこなす、というものである。どうやら古代から世界各地にこの慣習は存在し、19世紀ごろにも、少なくともロシアや日本では行われていた。
紀元前の『ギルガメシュ叙事詩』にはギルガメシュ王の暴政の一つとして「全ての民の初夜の権利を持つ、他人の妻を犯す」ことが挙げられており、古代ローマでも領主は特権として初夜権を持ち、逃れるためには結婚税を払わねばならなかった。九世紀のスコットランドのユーエン三世は「貴族の男性は全ての庶民の妻を自由に犯し、領主は領内に住む全ての女の処女を奪ってよい」という法を制定した。キリスト教会はこれを「貴族の当然の権利」として支持した。結婚式から三夜以内に花婿が花嫁と寝ることは「神の祝福を汚す肉欲的行為」であるが、領主の肉欲は「正しく相応しいこと」であるとし、領主より先に妻と寝た男は法で罰された。
何故こんなことを行ったかについては諸説ある。「男の好色による」「女性の所有権と土地所有権が等価とされていたため、領地に住む女たちは領主の所有物とみなされた(女性は家畜と同じに男の財産の一つとされ、人権が認められていなかった)」だとか。いずれにせよ、女性の人格を無視した権力ある男性の横暴と捉えられがちであり、実際、その一面もある。スコットランドの例や、かつてのアメリカの黒人奴隷の妻や娘たちになされた横暴などは、まさにそうだろう。
けれども、また別の見方もある。現在、処女は神聖視される傾向があるけれども、男の童貞は早く捨てることが望まれるのが一般的である。結婚する時に童貞のままの男性は、暗に馬鹿にされる傾向があるだろう。――ここに、初夜権の残る一面に関する答えは隠されている。つまり、(現在童貞に関して考えられているのと同じ感覚で)女が結婚に臨んで男を知らないままなのは恥ずかしいこと、性的に未熟で一人前ではないという考えがあったのである。
中山太郎の『日本婚姻史』に「南方熊楠氏が紀州の兵主で目撃されたのに、十四歳くらいの少女が風呂屋へ来て、十七、八歳の木挽の少年を付けまわし、種臼きってくだんせ、としきりに言うていた。この年頃になっても処女でいるのを大恥辱に思っているらしいとのことである」とある。「種臼きって」とは処女を奪って、という意味だ。
ユダヤ教やイスラム教、アフリカ、オセアニアなどには割礼の風習がある。概ね、男児の生殖器の包皮を手術で切り取って大人の造作にすることだが、これも「大人になるには肉体的にも成熟しているべき」という思想が一端にある風習だと思われる。トルコでは十歳前後の男子にこれを施し、豪華な帽子と晴れ着を着せて親戚に挨拶して回り近所を車で練り歩く。これは一種の成人式であると考えられるだろう。
同じように、処女膜を道具や手の指で切開する習俗もあった。日本の愛媛県北宇和郡の山村において、かつては娘が十四、五歳になると親は娘が早く女にならないものかと心配した。中には、酒を買って人に依頼しにいった親もあるという。このことを「アナバチワリ」といって、この依頼される人は村の中でなんとなく決まっていた。大抵は物静かで無口な男であり、常々畳や板に擦り付けて爪を磨いている。そうして三日ほど泊まらせて娘を《女にした》という。また、娘たちに対しては「陰毛が生えても処女のままだと、ひげの根で閉じ込められて《割れなくなる》んだぞ」と脅しつけて不安がらせ、アナバチを割る気にさせていたそうだ。これが済むと「さあ女になったから相手を世話してやろう」ということになり、嫁入りが決まる。よって、嫁入る時に処女だということは殆どなく、むしろ処女は悪いという風であった。他にも、アフリカでは人工的な陰核の除去や大陰唇・小陰唇の切開、そして破瓜(処女膜の切開)、いわゆる《女性器切除 Female Genital Mutilation 》が行われていた。文化人類学ではこれを「破素」と呼ぶ。
道具や手の指を使うのではなく、実際に性交することで破瓜をさせる風習もある。日本ではやはり「アナバチワリ」系の名で呼ばれることが多く、島根県簸川郡北浜村(現、平田市)では「十二、三歳の娘がまだ娘にならないうち(初経前)に五十以上の後家爺さんに大人にしてもらうことがあり、これを「ハチワリ」といった。これには世話した人がお歳暮を持っていった」とか、福井県城崎村(越前町)でも「アナバチといって、特定の者が十二、三歳の女子を一人前にして、若者の仲間に告げる風があった」という。アナバチワリは九州から福井県までの黒潮沿いの太平洋海域と、山口県から福井県までの対馬海流沿いの日本海海域に分布しており、南方を起源とする習俗らしい。実際、十三世紀末の中国人の記録によると、かつてのカンボジア王国には、娘を持った親たちが娘の結婚の前に仏教や道教の僧侶に頼んで娘の処女を破ってもらう、《チン・タン》という儀式が存在していた。これは年に一回、土地の知事が指定した特定の日に行われ、僧侶は年に一人の娘しか破瓜することは許されなかった。この儀式によって僧侶は手厚い報酬を受けたが、金持ちの娘は七、八歳でこれを済ませることが出来るのに(当時のカンボジアは早婚だった)、貧乏人の娘は報酬を用意できないために儀式を受けられず、婚期が十一歳頃まで遅れるものだったという。こんな貧しい人たちのためにチン・タンの費用を用立ててやるのは尊い行為とみなされていた。
念のために補足しておくと、男子の場合も女子と同じように、否が応なく年配者のところに連れて行かれて筆おろしをさせられていた。成人して若者組に入ると先輩に娘宿に連れて行かれて年長の娘に教えてもらうとか、お堂に村の既婚女性が集まって、集団で雑魚寝して少年たちに性の手ほどきをしたとか。なかなか上手くいかない若者もいて、一人前にするのは大変だったそうである。男性の場合、後の時代には風俗の女性のところに行って済ませることも多くなったようだ。
以上のように、処女を捨てておかねば結婚できない風潮があったわけだが、やがてこの風習は結婚の儀礼とまとめられ、結婚の前夜や初夜に花嫁が花婿とではなく、花婿の友人や舅や仲人と床を共にする、という形をも生み出した。
淡路の出島では結婚の前夜に花婿の最も親しい友人が花嫁を《天神様》と俗称される鎮守の社に誘い、そこで相姦する。陸前国社鹿郡石巻町近くの福井村では、結婚の前夜、かねてから花嫁に目をつけていた部落内の青年に花嫁が身を任せる。青年は花嫁を誘い出してもいいし、花嫁の家に忍び込んでもよい。家族もこれを公認していた。ボスニアでは、婚礼に出席する男性客は一人ずつ(夫婦の抱擁を比喩して)花嫁を壁に押し付ける習慣があった。
ここにはまた、村の娘はその村の若者たち全体の共有物である、という思想も現われている。結婚の前に娘は若者たちに分配され、ようやく夫個人の占有とするのが許されるのである。奥州のある村では、花嫁は結婚の前夜に親戚中の未婚の男子と交わらねばならなかったという。
豊後国日田郡夜明村大字夜明では、毎年八月十五日(明治以前は旧七日)に盆保々という行事を行った。この日は一村の男女が総出で綱引きをし、夜になると当年十四歳に達した娘は村の男のいずれかに必ず体を許さねばならない決まりだった。拒めば《穴無し》とみなされて誹謗され、縁談を拒まれたり婚期を遅らされたりした。加賀国能美郡でも娘を村の若者たちの共有とするのを許さない父兄があれば、若者たちが大挙してその家を襲って屋根をめくり、嫁入りの妨げをして婚期が遅れるようにつとめ、その家が困窮しても同情しないのを常としたという。越後国には明治四十五年まで盆カカ(または盆くじ)という行事が広く行われ、毎年盂蘭盆になると、村の若者がくじをひいて、この盆の間だけの妻を村の娘たちの中から定めた。娘たちは無条件でこれに従わねばならないのだが、若者が引き当てた娘を気に入らない場合には清酒一升で取り替えてもらえた。親たちはこれを公認し、これが縁になって正式に結婚するカップルも多かったそうである。
村の娘たちは村の若者組の管理下に置かれ所有されており、それを拒めば時には軟禁、ひどいときには村からの放逐もありえた。他の村の男と恋仲になっても大変で、村の若者たちに迫害された。これを許してもらうためには酒などの物品を上納せねばならなかった。
司馬遼太郎の『余話として』(文春文庫)に「話のくずかご――村の心中」というエッセイがあり、江戸初期の大阪辺り石川村大ヶ塚の庄屋の書き残した心中事件について述べている。村の男女が心中したが、男が女を殺した後に死に切れずに逃げ、その男を捕まえて村内裁判になった話である。ツナという十六歳の娘には八郎兵衛という恋人がおり、夜毎の夜這いを許している。しかしツナは六キロほど離れた須賀村に一年間奉公に出ることになった。恋しさを抑えきれない八郎兵衛は須賀村に通っていくが、須賀の若衆どもがこれに気づき、たとえ他所から来た奉公人にせよ村の娘は村の若衆の占有だとて、道に待ち伏せて嫌がらせをした。(これを書き残した庄屋は「道なき世にもあるかな」と憤慨している。)仕方なく、八郎兵衛は酒を買って上納したが、貧乏な家の出でたちまち金が底を尽き、ついに思い余ってツナに心中を持ちかけたのだった。
羽前国(現、山形県)の米沢市に近い萩村では、媒酌人がまず花嫁を《貰い受けて》自宅へ連れ帰り、三晩の間は自分の側で寝起きさせてから、百八個の丸餅を作り、それを背負って花嫁を連れて花婿の家に行って結婚式を挙げさせたというし、青森県庁に収蔵されていた明治七年三月の日付のある文書には「元南部領七戸通三沢村という村に限り、男女が結婚する時になると、媒の者が花嫁を夫家へ連れて行く。婚姻の夜は夫婦が床入りをせず、媒の男が花嫁を自分の妻同様にして寝て、その翌夜より本当の夫婦の床入りになる。これを口取という」とある。ロシアのチェルノゴーリエでも初夜の晩に花嫁と並んで眠るのは仲人だった。
このように、花婿以外の男性が先ず花嫁と床を共にするわけだが、中には男女一組の仲人や年配の女性一人が初夜の部屋で一緒に寝ることもある。下野国(現、栃木県)塩谷郡栗山郷では、婚礼の夜、花婿側も花嫁側もそれぞれ「お連れ様」なる者を同行させる。お連れ様には両親の揃った同性の者を選ぶ。初夜の晩、お連れ様は花婿花嫁と同じ部屋に寝るのが礼儀とされていた。津軽地方には「おくり婆様」なる役があって、花嫁が首尾よく《貫通された》のを見届けて親に報告するのが役目だったという。
以上、「性的にも成熟しなければ大人になったとはいえない――結婚資格は得られない」という視点で、結婚以前の破瓜、初夜権についての事例を挙げてみた。けれども、また別の解釈もある。
千葉県君津郡では、娘の結婚が決まると父親か母親が村の若者頭に酒を一升持っていって「うちの娘はまだ生娘なので、どうか娘にしてやって欲しい」と頼んだという。この地域では「生娘は怖い、生娘を嫁にもらうのは大変怖いことだから、娘にしてもらわねば困る」と言っていた。そして娘にする役の若者頭は「エビス神」だとか「道祖神」などと呼ばれることがあったという。
カンボジアで処女を破る役を与えられているのは僧侶であり、日本でも年寄りにその役が与えられるのがよく見られる。それは、彼らが処女の血の呪力に対抗できるシャーマン〜神に近い者であることを示すと同時に、彼ら自身が巫女の夫たる《神》の化身であることを示唆している。いや、千葉県君津郡の若者頭の例のように、それが村の若者であっても通りすがりの旅人であっても、処女を抱いているとき、彼らは《神》の化身であると考えられていたのだ。
以上のような信仰は、説話でしばしば未婚の娘が怪物(竜)に連れ去られたり生贄に捧げられたりして、塔や洞窟で怪物と一緒に暮らしている――その妻になっている点にも現われているかもしれない。彼女たちは一度神婚し、その後に初めて普通の花嫁になれるのだ。
性交を神婚と見る思想は、神殿娼婦を生み出した。
ヘロドトスの『歴史』によると、バビロニアの女たちはどんな身分の者であろうと必ず、一生に一度はミュリッタ(愛の女神イシュタル〜ヴィーナス)の巫女として、神殿で見知らぬ男と交わる風習であった。彼女たちは座って待ち、男たちは通路を通ってきて好みの女を物色し、選んだ女の膝に銀貨を投げる。金額は決まっていない。女の方には拒否権も選択権もない。選ばれるまでは帰宅は許されず、美しい女はすぐに帰宅できたが、そうでない女は長い間そこにいなければならなかった。この交わりはあくまで一度のもので、もしも後で交わった男が再び誘いをかけてきても、女は決して応じることはなかったという。同様の風習はエジプトやギリシアを始めとする地中海の国々、インドにもあったとされる。
神殿娼婦という風習は、見知らぬ男――神の化身と神婚し、豊穣(子宝)の力を得ることが目的だと思われる。日本にも祭礼の日に村中の者が自由に乱交し拒否できない風習のある地域が多数あったが、そのうち茨城県北相馬郡文間村大字立木の蛟[虫罔]神社の祭礼では、多くの男と交わるほど体が丈夫になる、いい婿が得られるといって、既婚未婚の差なく、女たちがその祭礼中誰彼かまわず肌を許していたという。これらは「縁結び、子宝の神」の行事とされ、神に許されているアソビなのだから倫理的にも問題ない、とされていた。このように、神殿娼婦たちは快楽や生活の糧のために春をひさぐのではなく、女神の化身として豊穣を呼ぶ神婚――神事を行っていたのである。
処女は神の妻であり、人間の夫の前に神と神婚せねばならない。三河国南設楽郡長篠町付近の村落では、結婚の当夜は「おえびす様にあげる」として夫婦は同衾しなかったし、能登国の鳳至・珠洲の村では結婚式に花婿は列座しない。ベトナムのチャム族・バチャムでは新婚夫婦は同じ部屋に起居するが三日間は性交を禁じられる。九世紀のスコットランドのように、夫は神に初夜権を譲り渡し、妻に触れることを遠慮するのである。
日本には「初子は親に似ない」という言葉がある。初夜の交わりによって生まれた子は、神…一族の祖霊から授かった子、という扱いだったのだろう。
「ヴォルスンガ・サガ」や[二人兄弟]に「純潔の刀」と呼ばれるモチーフが出てくる。男女が同じ床に寝るとき、二人の間に抜き身の剣を置いて、花嫁の真の夫に対して操を立てる、というものである。「フェアとブラウンとトレンブリング」では変形していて、夫が真の妻に操を立て、かつ、神意を伺うためのものになっている。
実はこれは、西欧において祖霊をかたどった木彫りの人形を、新婚の床で花婿と花嫁の間に置いた慣習から来ているのだと、プロップは『魔法昔話の起源』で述べている。木彫りの人形を新婚の床に入れるのは、花婿より先に祖霊(神)が花嫁と交わることを意味すると考えられる。なお、ベトナムのチャム族・バニでは、新婚夫婦は三日間妻の部屋で起居するが、その間、夫婦の寝床の中央には檳榔子とキンマを載せた盆が置かれ、何者も動かすことは許されない。三日が過ぎると仲人が来てこれを片付け、ようやく夫婦同衾の運びとなる。
十二世紀にアイスランドで成立したとされる「ラグナル・ロズブロークのサガ」には、花嫁が神々に許されるまではと言って、三日の間は性交を拒もうとするエピソードがあり、興味深い。
主な参考文献
「グリムのメルヘン「いばら姫」(KHM 50)解釈について : その文献学的, 教育学的考察」 岡本英明著/『大学院教育学研究紀要3』 九州大学大学院人間環境学研究科発達・社会システム専攻教育学コース 2001.
『ねむり姫の謎 糸つむぎ部屋の性愛史』 浜本隆志著 講談社現代新書 1999.
『婚姻の民俗 東アジアの視点から』 江守五夫著 吉川弘文館 1998.
『遊女と天皇』 大和岩雄著 白水社 1993.
『ヴェトナム少数民族の神話 チャム族の口承文芸』 チャンヴェトキーン編、本多守訳 明石書店 2000.
『魔法昔話の起源』 ウラジーミル・プロップ著、斎藤君子訳 せりか書房 1983.
『妖精の誕生 ―フェアリー神話学―』 トマス・カイトリー著 市場泰男訳 教養文庫 1989.
『ギリシアの神話 神々の時代』『ギリシアの神話 英雄の時代』 カール・ケレーニイ著 植田兼義訳 中公文庫 1985.
『ギリシア・ローマ神話辞典』 高津春繁著 岩波書店 1960.
Copyright (C) 2003,2008 SUWASAKI,All rights reserved.
円環伝承 > 民話想 > 眠り姫 > 眠り姫のあれこれ・前半 > 眠り姫のあれこれ・後半